
歯科コラム詳細dental-column
歯科
妊娠中に歯医者へ行っても大丈夫?マタニティ歯科の疑問に歯科医師が全回答!
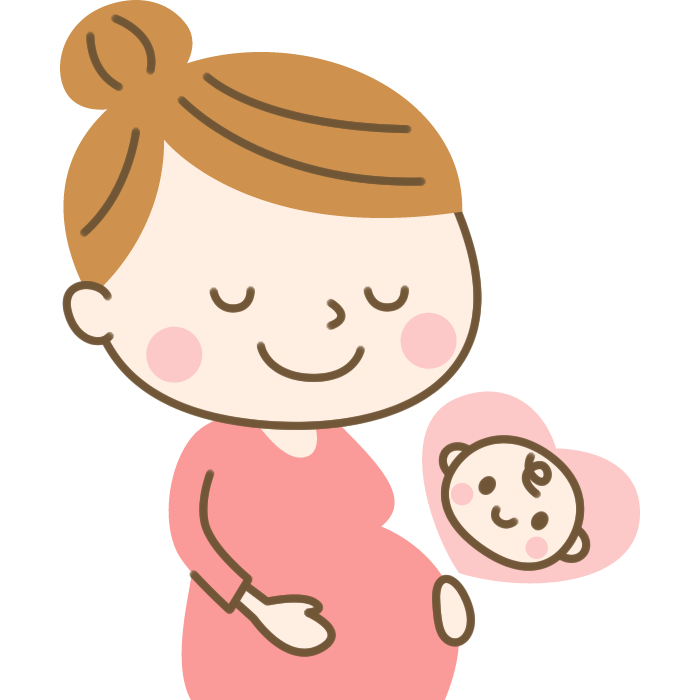
【この記事の監修歯科医師】
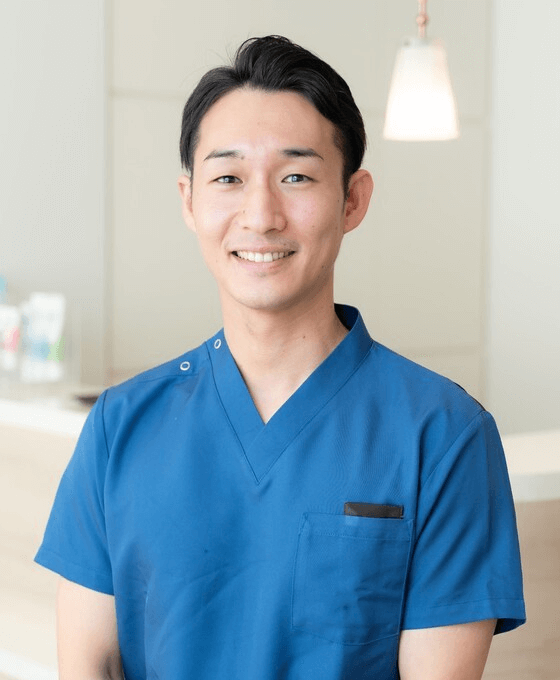
神奈川歯科大学卒業。
公益社団法人 日本口腔外科学会 認定医。
「再治療のない、丁寧な治療」をモットーに日々情熱を注いでいます。
歯科のお悩みならなんでもご相談ください。
妊娠中に歯が痛くなったり、歯茎が腫れたりしても、「お腹の赤ちゃんに影響があるのでは?」と不安で歯医者に行くのをためらっていませんか?
実は、妊婦さんこそ歯科検診や適切な治療がとても大切。
この記事では、現役歯科医師がマタニティ歯科診療について、安全性やタイミング、よくある症状への対処法まで分かりやすく解説します。
妊娠中に歯科に通っても大丈夫?よくある不安に答えます
妊婦でも歯医者に行って大丈夫?受診のタイミングと注意点
もちろん、妊娠中でも歯科に通うことは基本的に大丈夫ですし、むしろ推奨されることも多いです。
妊娠中はホルモンバランスの変化によってお口のトラブル(歯ぐきの腫れ・出血、虫歯の進行など)が起きやすいため、定期的なチェックとケアがとても大切です。
妊娠中でも歯医者に行っていいのか
妊娠中でも歯科受診は問題ありません。
ただし、安定期(妊娠5〜7ヶ月頃)が最も安心して治療を受けやすい時期とされています。
どんな治療なら妊娠中でもできるのか
基本的な治療(虫歯治療、歯石除去、歯周病ケアなど)は可能です。
安定期におすすめの治療
- 虫歯治療(軽度~中程度)
- 歯周病予防のクリーニング
- 親知らず以外の歯の痛みへの対処
念のため避けた方がよい治療
- 長時間の外科的処置(親知らずの抜歯など)
- 強い痛み止めや抗生物質を使う治療
麻酔・レントゲンは赤ちゃんに影響ない?医師の見解
歯科用の局所麻酔は、赤ちゃんに影響するのか
基本的に安全とされています。
歯科治療で使われるのは、局所麻酔(リドカインなど)がほとんどです。
これは歯の周囲のみに作用し、全身に広がる量はごくわずか。
胎児に影響する可能性は非常に低いとされています。
歯科治療では、妊娠中でも使用可能な麻酔薬が選ばれており、アドレナリン入りの麻酔も、適量であれば問題ないという見解が日本歯科麻酔学会などからも出されています。
ただし、高血圧症など合併症がある場合は、使用薬剤を変更することもあります。
レントゲン撮影はしても問題ないのか
歯科レントゲンの放射線量は、以下で使われる放射線量に比べて極めて少なく、パノラマ(全体)の場合、0.03㎜㏜、デンタル(部分的)の場合、0.01㎜㏜です。
これは、自然界から1年間に受ける放射線量のおよそ40〜100分の1程度と非常に少ないです。
また、照射部位が口元に限られており、腹部からは遠いため、胎児への影響はほぼないとされています。
撮影時は鉛の防護エプロンを着用することで、腹部への放射線被ばくをさらに減らすことが可能です。
レントゲン撮影により、肉眼では確認できない歯の根の部分や、歯の裏側の部分なども見ることができ、より精度を上げた検査が可能になります。
治療できる時期は?妊娠初期・中期・後期それぞれの違い
妊娠中、「歯が痛いけれど、治療を受けてもいいのかな?」と不安になる方は少なくありません。
実は、妊娠中でも歯科治療は可能です。
ただし、治療を受けるタイミング(妊娠の時期)によって、注意すべき点や治療内容に違いがあります。
妊娠初期(0〜15週ごろ):慎重に経過をみる時期
妊娠初期は、胎児の重要な器官が形成される「器官形成期」にあたります。
この時期は、薬剤や強いストレスの影響を受けやすく、また、つわりがあることで治療が難しい場合もあります。
医療機関での対応
- 応急的な処置を中心に対応
- 本格的な治療は可能な限り妊娠中期以降に延期
- 検診や歯磨き指導
妊娠中期(16〜27週ごろ):治療に最も適した「安定期」
妊娠中期は、胎盤が完成し、体調も比較的安定する時期です。
つわりも落ち着くことが多く、最も安全に歯科治療を行えるタイミングとされています。
この時期におすすめの治療
- 虫歯・歯周病の本格的な治療
- 歯石除去や定期的なクリーニング
- 初期に応急処置のみ行った症例の継続治療
歯や歯ぐきの健康を保つことで、妊娠中の合併症リスク(例:早産・低体重児)を下げるという報告もあります。
妊娠後期(28週以降):無理のない範囲で対応を
妊娠後期になると、お腹が大きくなり、仰向けでの治療がつらくなる場合があります。
さらに、治療によるストレスが早産の引き金になる可能性もあるため、原則として応急処置にとどめるケースが多くなります。
後期に可能な処置
- 強い痛みがある場合の応急的な処置
- 短時間で終わるシンプルな治療
- 歯科医・産科医と連携しながら慎重に判断
妊娠中に多いお口のトラブルとその原因
妊娠性歯肉炎とは?出血しやすくなるのはなぜ
妊娠中は心と体にさまざまな変化が起こる時期。
実は、お口の中にも特有のトラブルが起こりやすくなることをご存知でしょうか?
その代表的なものが、「妊娠性歯肉炎」です。
「歯ぐきが腫れる」「出血しやすい」といった症状が見られ、妊婦さんの約半数以上が経験するともいわれています。
妊娠期に多く見られる口腔トラブルの原因や対策について、解説します。
妊娠性歯肉炎とは?
妊娠中にホルモンの影響で起こりやすくなる、歯ぐきの炎症のことです。
歯ぐきが赤く腫れたり、歯みがきの際に出血しやすくなったりするのが特徴です。
主な症状としては、「歯ぐきの腫れやむずがゆさ」「歯みがきや食事中の出血」「口臭が気になる」などです。
初期は自覚症状が乏しいため、知らず知らずのうちに進行しているケースもあります。
なぜ妊娠中は歯ぐきが炎症しやすいのか
ホルモンバランスの変化が主な要因となります。
妊娠中は、エストロゲンやプロゲステロンといったホルモンが増加します。
これにより、歯肉の血流が増えて炎症が起きやすくなるのです。
ホルモンの変化により、口内に存在する細菌のバランスが変わり、歯周病菌が増殖しやすくなるともいわれています。
また、 唾液の変化とつわりの影響もあります。
妊娠中は唾液が粘つきやすくなることがあり、口腔内の自浄作用が低下します。
つわりで歯みがきが十分にできないことも、プラーク(歯垢)を溜めやすくする要因です。
こうした要素が重なり、歯肉炎のリスクが一気に高まるのが妊娠期の特徴です。
放っておくとどうなる?──母体と胎児への影響
妊娠性歯肉炎をそのままにしておくと、本格的な歯周病に進行する可能性があります。
さらに最近では、重度の歯周病が早産や低体重児出産のリスクを高めることも指摘されています。
つわりで歯が磨けない!どうすればいい?
「歯みがきしようとすると気持ち悪くなる……」
「歯ブラシを口に入れるだけで吐き気がする……」
妊娠初期の「つわり」は、日常生活にさまざまな支障をもたらしますが、口腔ケアにも大きな影響を及ぼすことがあります。
つわり中でも無理なくできる口腔ケアのコツをご紹介します。
なぜつわりで歯みがきがつらくなる?
つわりの原因は明確には解明されていませんが、妊娠初期に急激に増えるホルモン(hCGなど)の影響や、自律神経の変化が関係していると考えられています。
歯みがきがつらくなる原因としては、
「歯ブラシの感触や匂いに敏感になる」
「口の中に何か入れると吐き気が誘発される」
「歯みがき粉の香りが苦手になる」
といったことがあげられます。
歯みがきができないとどうなるの?
つわり中は、食事の回数が増えたり、酸っぱいものを好んだりすることが多く、その一方で歯みがきがしっかりできないと、虫歯や歯肉炎のリスクが高まることになります。
特に注意したいのは「妊娠性歯肉炎」。
妊婦さんの約半数が経験するといわれる、妊娠特有の歯ぐきの炎症です。
無理しない歯磨きの工夫
1. タイミングを工夫する
食後すぐでなく、体調が落ち着いている時間帯に磨く
寝る前の1回だけでも丁寧にみがくことを意識する
2. 歯磨き粉を変える or 使わない
無香料・低刺激の歯磨き粉に変えてみる
どうしても無理な場合は、水だけでブラッシングでも問題ありません
3. ヘッドが小さい歯ブラシを使う
奥まで入れずに済むので、小さめの歯ブラシがおすすめです
4. どうしてもつらいときは代替ケアを
磨けない場合は、フッ素入りの洗口液(マウスウォッシュ)を使う
食後に水やお茶でうがいをこまめにするだけでも違います
歯磨きは、完璧を目指すより、“できる範囲で継続する”ことが大切です
妊娠中の虫歯・親知らず・歯のぐらつきの対処法
妊娠すると、身体だけでなく口腔内にもさまざまな変化が起こります。
虫歯が進行しやすくなったり、親知らずの痛みが出てきたり、「歯がぐらぐらしてきた」と感じることも。
これらの症状は、放置すると母体や赤ちゃんに影響する場合もあるため、適切な時期と方法で対処することが大切です。
妊娠中に起こりやすい口腔トラブルとその対処法について、医療的観点から解説します。
虫歯になりやすい妊婦さん、その理由とは?
妊娠中は、
「つわりで歯磨きが困難になる」
「食事や間食の回数が増える」
「唾液の性質が変わり、口の中が酸性に傾く」
「免疫力の低下で細菌が繁殖しやすくなる」
などの理由からむし歯リスクが高まります。
自分ができる対処法としては、体調がよいときにこまめに歯みがきを行う、フッ素入りの洗口液やジェルの併用などがあります。
しかし、対策していてもむし歯ができてしまい、痛みが強い場合は、妊娠中期(安定期)に治療を検討します。(局所麻酔やレントゲンは、適切に使用すれば胎児への影響は極めて少ないとされています)
親知らずの痛み・腫れが出たら?
親知らずは、妊娠中のホルモン変化や免疫力低下により炎症を起こしやすくなります。
「急に腫れて食事がとれない」「ズキズキとした痛みがある」といった症状は、智歯周囲炎(ちししゅういえん)の可能性があります。
対処法としては、腫れや痛みがある場合は、早めに歯科受診してください。
妊娠中の抜歯は原則避けますが、炎症が強い場合は安定期に対応することもあり得ます。
炎症コントロールのため、抗生物質や鎮痛薬が処方されることもあります。
ただし、 妊婦でも使用可能な薬を選択するので、自己判断で市販薬を使うのは避けましょう。
「歯がぐらつく」…それって異常?
妊娠中は、エストロゲンやプロゲステロンといったホルモンの影響で、歯ぐきの組織がゆるみやすくなります。
その結果、「歯が浮いた感じがする」「噛むと違和感がある」と感じることもあります。
これは「妊娠性歯周炎」の可能性があり、悪化すると歯周病に進行するおそれもあります。
対処法としては、丁寧なブラッシングと定期的な歯科チェックを行うことが大切です。
歯の動揺が強い・出血が多い場合は、妊娠中期に歯周治療を行うこともできます。
出産後は自然に症状が改善することが多いですが、産後もケアの継続を行うことで安定した歯ぐきを手に入れることができます。
マタニティ歯科診療とは?
マタニティ歯科診療とは、妊娠中の体と心の変化を考慮しながら行う、妊婦さんのための特別な歯科ケアのことです。
ホルモンバランスの変化やつわり、免疫力の低下によって起こりやすい口腔トラブルに対し、妊娠期の安全なタイミングで無理のない範囲で治療・予防処置を行います。
妊婦さん専用の診療メニューと流れ
「妊娠してから歯ぐきが腫れたり、出血しやすくなった」
「つわりで歯磨きがつらい」
「むし歯や親知らずの痛みが気になる」
「出産前に口の中をリセットしておきたい」
「妊娠中に受けられる治療の範囲を相談したい」などにおすすめしております。
マタニティ歯科診療の主な内容
1. 妊婦歯科健診(スクリーニング)
- 歯や歯ぐきの状態をチェック
- 妊娠性歯肉炎や虫歯の有無を確認
- 必要に応じて産婦人科との連携
2. 予防処置
- 歯みがき指導(つわりに配慮した方法)
- 専用器具によるやさしいクリーニング
- フッ素塗布や、口腔内の乾燥予防対策
3. 症状に応じた処置(安定期推奨)
- 虫歯や歯周病の治療
- 痛みのある親知らずの応急処置
- 必要に応じてレントゲン・麻酔(胎児に配慮した方法で実施)
診療の流れ(初診の例)
①受付・問診票記入 → 妊娠週数、産婦人科名、体調、既往歴などを記載
②カウンセリング・診査 → 妊婦さんの悩みや不安を丁寧にヒアリング
③お口の状態チェック → 歯科医師または歯科衛生士が優しく確認します
④予防・ケアの提案 → 安全な範囲で、今できることを一緒に計画
⑤必要に応じて治療スケジュールの相談 → 安定期(16〜27週)に治療を計画する場合あります
妊娠中に歯科検診を受けるべき理由
口腔環境が赤ちゃんに与える影響とは?
妊娠期間中は母体の身体にさまざまな変化が生じますが、その中でも見落とされがちなのが「口腔内の健康状態」です。
実は、妊娠中の歯や歯茎のトラブルは、母体だけでなく胎児の発育にも深く関わっている可能性があることが、近年の研究により明らかになってきました。
母体の口腔細菌の胎児へ影響
一部の研究では、歯周病菌や炎症性物質が胎盤を通過し、胎児に影響を与える可能性も指摘されています。
こうした感染や炎症の連鎖は、胎児の発育遅延や免疫異常のリスクにも関与する恐れがあります。
新生児への虫歯菌の母子感染
生まれたばかりの赤ちゃんの口腔内には虫歯菌(ミュータンス菌など)は存在しません。
しかし、母親の口腔内に虫歯菌が多い場合、スキンシップや食器の共有などを通じて菌が移ることがあります。母親の口腔環境が整っていることは、赤ちゃんの将来の虫歯予防にもつながります。
歯周病と早産・低体重児リスクの関係
妊娠中はホルモンの変化によって歯肉が敏感になり、妊娠性歯肉炎や歯周病が悪化しやすい傾向があります。
歯周病と全身への影響
歯周病は口の中の問題にとどまらず、慢性炎症性疾患として全身に影響を及ぼすことがわかっています。
歯周病によって産生される炎症性サイトカイン(IL-6、 TNF-α、 プロスタグランジンE2など)が血流を介して全身を巡ることで、他の臓器や組織に炎症反応を引き起こすことが知られています。
歯周病と妊娠:早産・低体重児出産との関連
多数の疫学研究・臨床研究により、重度の歯周病を有する妊婦は、そうでない妊婦と比べて早産や低体重児を出産するリスクが高いと報告されています。
考えられるメカニズム
- 炎症性物質の血流への流入
歯周病によって発生するサイトカインが胎盤に到達すると、子宮収縮や胎児発育の抑制を引き起こす可能性があります。
- 歯周病菌の血中移行
歯周ポケットから歯周病菌(例:Porphyromonas gingivalis)が血管内に侵入し、子宮・胎盤に影響を及ぼすケースも示唆されています。
- 免疫反応の過剰な活性化
歯周病によって母体の免疫応答が過剰に活性化し、胎児を守るべきバリアが弱まる可能性があります。
実際のリスク指標
- 歯周病がある妊婦は、早産のリスクが約2〜7倍に上昇するとの報告あり
- 低出生体重児(2,500g未満)を出産する確率も高くなるとする研究も複数存在
※ただし、因果関係の完全な解明にはさらなる研究が必要とされます。
出産後は時間が取れない!今のうちに整えるメリット
赤ちゃんが生まれると、昼夜を問わずの授乳・おむつ替え・寝かしつけ……と、育児に追われる日々が始まります。
「歯が痛いな…」と思っても、通院の予定を立てる余裕すらなく、症状を我慢してしまうママは少なくありません。
特に乳児期の赤ちゃんを連れての歯科受診は、時間や環境の確保が難しく、痛みが限界に達してからの緊急受診になってしまうケースもあります。
そうならないためにも妊娠前、妊娠中の適切な時期に早めの対策を行うことが大切です。
早めの歯科受診をおすすめする理由
- 虫歯・歯周病の早期発見・早期治療
妊娠中期(16〜27週頃)は体調も安定しやすく、歯科治療を受けやすいベストタイミングです。
妊娠性歯肉炎や初期の虫歯はこの時期にチェック・処置しておくと、出産後のトラブルを未然に防げます。
- 赤ちゃんへの感染予防にもつながる
母親のお口の中に虫歯菌が多いと、赤ちゃんへの母子感染のリスクが高まります。
妊娠中に口腔内を清潔に整えておくことで、赤ちゃんの虫歯予防にも効果的です。
- 自分自身が快適に過ごせる
妊娠後期〜出産直後は、身体的にも精神的にも大きな負担がかかります。
お口の中の違和感や痛みがないことは、ストレス軽減と快適な妊娠・出産生活のサポートにもつながります。
実際にあったマタニティ患者さんの診療事例
ケース①:妊娠5ヶ月で歯ぐきが腫れてしまった Aさん(30代・初産)
〈症状〉
妊娠中期に入り、ある日突然「右下の歯ぐきがぷっくり腫れて痛い」と来院。
熱はなく、歯はグラグラしていなかったが、歯ぐきが赤く、軽く触れるだけでも出血。
〈 診断〉
妊娠性歯肉炎(ホルモン変化による炎症)。
歯周ポケットにプラーク(細菌の塊)の停滞あり。
〈処置〉
やさしく歯石除去(超音波スケーラーを弱設定)した後、炎症部位の洗浄・消毒
母体に影響のない安全なうがい薬を処方。
現在の歯磨きの回数などを確認し、歯磨き方法の見直し・柔らかめのブラシを推奨。
その後、定期的に来院し口腔内の定期的な管理を行った。
〈患者さんの コメント〉
妊娠してから歯ぐきが敏感で出血しやすいと思ってたけど、こんなに腫れるなんてびっくりでした。
正しいケアと処置で、1週間ほどで腫れも改善しました。
その後も定期的に来院し口の中の状態をキレイにすることで出産後まで安定して経過観察できました。
ケース②:妊娠後期に虫歯が痛くなった Bさん(20代・経産婦)
〈症状〉
妊娠8ヶ月、冷たいものがしみていた奥歯がズキズキと痛むように。
市販の鎮痛剤も使えず、夜も眠れずに受診。
〈診断〉
奥歯の虫歯が神経まで進行(C3レベル)
早期治療が必要な状態
〈処置〉
妊娠後期だったため、体勢や胎児の負担に配慮しながら短時間で治療。
安全な局所麻酔を使用し、神経を除去する根管治療を実施。
鎮痛薬は産婦人科医とも連携して処方した。
〈患者さんのコメント〉
もっと早く来ればよかった…妊娠中でも麻酔してもらえるんですね。
処置後はすぐに痛みが取れ、安心して出産を迎えられました。
ケース③:妊娠初期の健診で虫歯が見つかった Cさん(30代・初産)
〈症状〉
特に自覚症状なし。
市の妊婦歯科健診で来院。
チェックしたところ、上の奥歯に2本の小さな虫歯が見つかる。
〈処置〉
妊娠初期のため、無理な治療は避け、経過観察を行い、妊娠中期(安定期)に入ってから、低侵襲のレジン(樹脂)治療で完了。
食生活のアドバイスと、妊婦向けのフッ素ケア、歯磨きの方法を指導した。
〈患者さんのコメント〉
自分では気づいてなかったので、健診受けて本当によかったです。
よくある質問(FAQ)
妊娠中でも麻酔や薬は使える?
使えます。
ただし、安全性に配慮しながら「使える薬・避ける薬」「タイミング」を見極めて治療します。
妊婦健診で歯科検診も受けられるの?費用は?
はい、本当です。
多くの市区町村では、妊婦さん向けの「無料歯科検診」を実施しています。
緊急時にどうすればいい?予約は必要?
まずは落ち着いて、歯科医院に連絡をしてください。
妊娠中でも、歯の急な痛み・腫れ・出血などは我慢せず、早めに歯科を受診しましょう。
歯科医院に電話する際は、必ず「妊娠中であること」「週数(例:妊娠〇週)」を伝えてください。
歯科側が、麻酔や薬、診療体制などを配慮して対応します。
基本的には「要予約」です。
妊婦さんの場合、診療時間やチェアの姿勢などに特別な配慮が必要なため、事前に予約を取っていただくと安心・安全です。
ただし、強い痛み・出血・顔の腫れなど緊急性が高い場合は、その旨を伝えれば当日対応できる医院も多くあります。
まとめ
歯科治療は“痛くなってから”ではなく、妊娠中こそ“予防”が大切です。
特に妊娠中期(16〜27週)は治療に適した時期。
気になる症状があれば、早めに歯科医院に相談しましょう。
当院は大倉山駅から徒歩1分でアクセスも良く、実績も豊富です。
口腔外科専門医の資格を持った医師が治療を行いますので、安心して治療をお受けいただけます。
まずはお気軽にご相談ください!
