
歯科コラム詳細dental-column
歯科
歯科医が教える歯周病セルフケア|本当に効果的な方法と限界を知る

【この記事の監修歯科医師】
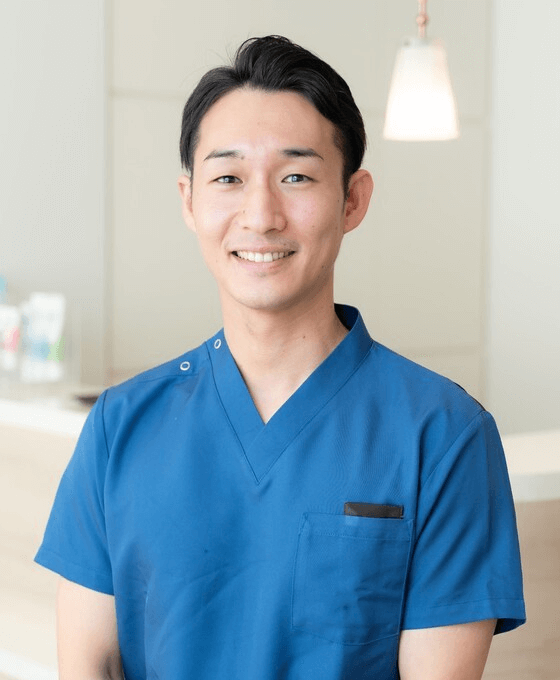
神奈川歯科大学卒業。
公益社団法人 日本口腔外科学会 認定医。
「再治療のない、丁寧な治療」をモットーに日々情熱を注いでいます。
歯科のお悩みならなんでもご相談ください。
歯茎の出血や腫れ、口臭など歯周病の症状にお悩みではありませんか?
歯周病は日本人が歯を失う最大の原因ですが、適切なセルフケアで予防・改善が可能です。
しかし、間違った方法では効果が得られず、症状が悪化することも。
本記事では、現役歯科医が患者さまに実際に指導している正しい歯磨き方法から効果的な歯磨き粉の選び方、さらにセルフケアの限界まで詳しく解説します。
毎日のケアを見直して、健康な歯茎を取り戻しましょう。
歯周病セルフケアの基礎知識
歯周病とは?進行段階と症状の見分け方
1.歯周病とは?
歯周病は、歯を支える「歯ぐき(歯周組織)」の炎症が進行していく病気です。
初期は自覚症状がほとんどありませんが、放置すると歯を支える骨が溶けて歯がぐらつき、最終的には抜けてしまうこともあります。
2.歯周病の進行段階と主な症状
歯周病は、進行段階ごとに症状や治療法が異なります。
以下に、歯周病の主な進行段階とその特徴をまとめます。
| 段階 | 病名 | 主な症状 | 状態の説明 |
| 1段階目 | 歯肉炎 | ・歯ぐきが赤く腫れる・歯磨き時に出血しやすい | 歯ぐきのみに炎症がある状態歯槽骨の破壊はまだない |
| 2段階目 | 軽度歯周炎 | ・歯ぐきが下がりはじめる・歯周ポケットが深くなる(3~4mm)・口臭が気になる | 歯周組織の破壊が始まり、歯槽骨が一部吸収されている状態 |
| 3段階目 | 中等度歯周炎 | ・歯ぐきの腫れが強い・歯のグラつきが始まる・歯周ポケットがさらに深くなる(5~6mmに) | 歯槽骨の吸収が進み、歯が少し動くようになる。さらに口臭や出血が目立つ |
| 4段階目 | 重度歯周炎 | ・歯が大きく動く・噛むと痛い・膿が出る・歯が抜けそうになる | 歯槽骨が大きく失われ、歯の保存が困難になることも抜歯が必要になることもある |
セルフケアでできること・できないこと
歯周病は、初期には痛みもなく静かに進行する“サイレント・ディジーズ(静かなる病)”とも呼ばれています。
そこで、毎日のセルフケアとセルフケアの限界、プロのケアの重要性についてご紹介します。
セルフケアでできること
1.正しい歯磨きで「歯垢」を残さない
歯周病の最大の原因は「歯垢(プラーク)」です。
歯ブラシは、毛先を歯と歯ぐきの境目に当て、優しく小刻みに動かしましょう。
1日2〜3回、1回3分以上が目安です。
2.歯間ブラシ・デンタルフロスを活用しよう
実は、歯ブラシだけでは歯の汚れの約6割しか取れていないと言われています。
そのため歯と歯の間は、歯間ブラシやデンタルフロスを使って補いましょう。
3.殺菌成分配合の歯磨き粉・洗口液を取り入れる
市販の製品でも、塩化セチルピリジニウム(CPC)やクロルヘキシジン(CHX)などの成分が含まれたものは、細菌の繁殖を抑える効果が期待できます。
ただし、「歯磨き粉に頼るだけ」では不十分です。
あくまで補助的な役割と考えましょう。
4.喫煙・糖尿病は歯周病を悪化させます
喫煙や糖尿病は、歯周病のリスクを高める大きな要因です。
お口の健康を守るためにも、生活習慣の見直しはとても大切です。
5.定期的にプロのチェックを
セルフケアで取りきれない歯石や見えない部分の汚れは、歯科医院でのクリーニング(PMTC)が効果的です。
セルフケアだけでできないこと
1.セルフケアでは取れない「歯石」の存在
どれだけ丁寧に歯磨きをしても、歯垢が石のように硬くなった「歯石」は、ご自宅のケアでは取り除けません。
歯石の表面には細菌が繁殖しやすく、炎症を引き起こす原因になります。
しかも、歯ぐきの中(歯周ポケットの奥)に付いた歯石は、見えないうえに深くて手が届きません。
そこで歯石は、歯科医院で専用器具(スケーラー)を使って安全・確実に除去する必要があります。
2.歯周ポケットの深さは自分ではわからない
歯周病の進行度を見極めるポイントのひとつが、歯と歯ぐきのすき間=歯周ポケットの深さです。
しかし、この深さは見た目だけでは判断できません。
歯科医院では、専用の「プローブ」という器具で正確に測定し、進行状況に応じた治療を行います。
3.噛み合わせの乱れや歯並びによる汚れの蓄積
歯並びが悪かったり、噛み合わせに問題があると、磨き残しのリスクが高くなります。
また、知らないうちに歯に過剰な負担がかかり、歯周組織がダメージを受けやすくなることも。
こうした状態は、セルフチェックでは見つけにくく、歯科医師の診断が必要です。
4.「歯ぐきの中」の感染には専門的な処置が必要
進行した歯周病では、歯ぐきの内部や骨にまで細菌が入り込んでいることがあります。
その場合、通常のブラッシングでは届かず、抗菌処置や外科的な治療が必要になることも。
症状が進むと抜歯が必要になるケースもありますが、早期発見・早期治療で歯を守ることが可能です。
歯科医が実践指導している正しい歯磨き方法

基本のブラッシング技術
〈ポイント〉
- 歯ブラシは小さめ、毛先は柔らかめが理想
- 歯と歯ぐきの境目(歯周ポケット付近)に毛先が届くように意識する
- 1箇所あたり20〜30秒程度、ゆっくり動かす
- 力は強く入れすぎず、軽い力で小刻みに動かすことが重要
〈手順〉
- 歯ブラシを45度の角度で歯と歯ぐきの境目に当てる
- 小刻みに細かく動かしてプラークをかき出すイメージで磨く
- 歯の表面(外側・内側)全体をムラなく磨く
- 噛み合わせ面は軽く往復させるように磨く
- 舌や口の中の粘膜もやさしくブラッシングすると口臭予防に効果的
歯周ポケットを意識した毛先磨きのコツ
〈なぜ大事?〉
歯周病菌は歯と歯ぐきの境目に潜みやすく、ここをしっかり磨けないと歯周病が進行しやすくなります。
〈コツ〉
- 歯ブラシの毛先を歯周ポケットの奥に軽く入れ込むイメージで当てる
- 強く押し込まず、毛先が柔らかく動く範囲で丁寧に磨く
- 歯ぐきを傷つけないように優しく、振動を与えるように動かす
- 歯ブラシだけで届きにくい部分は、デンタルフロスや歯間ブラシも併用
〈よくある間違いと注意点〉
| 間違い例 | 理由・リスク |
| ゴシゴシ強く磨く | 歯ぐきが傷つき、逆に炎症・退縮の原因に |
| ブラシの当て方が水平 | 歯周ポケットの汚れを落としにくい |
| 磨く時間が短すぎる | プラーク除去が不十分になる |
| 舌や内側の掃除をしない | 口臭の原因になる |
歯周病予防に効果的な歯磨き粉の選び方
歯科医が推奨する有効成分とその効果
歯周病の予防や進行を防ぐには、正しいブラッシング習慣に加えて、効果的な成分を含むケア製品の活用が重要です。
市販の歯磨き粉やマウスウォッシュの中にも、歯ぐきの健康を守る成分が数多く含まれています。
歯周病予防に役立つ歯磨き粉の有効成分と効果
| 成分名 | 効果・特徴 |
| 抗炎症成分 (IPMP、グリチルリチン酸など) | 歯ぐきの炎症を抑え、出血や腫れを軽減 |
| 殺菌成分 (クロルヘキシジン、塩化セチルピリジニウムなど) | 歯周病菌の増殖を抑制し、歯肉炎や歯周炎の進行を防ぐ |
| 酵素 (リゾチーム、ラクトフェリンなど) | プラークの分解を助け、口内環境を整える |
| フッ素 (フッ化ナトリウムなど) | 虫歯予防の基本成分だが、歯周病にも間接的に有効 |
| 硝酸カリウム | 歯の知覚過敏予防にも役立ち、快適なブラッシングをサポート |
市販vs歯科医院専売:どちらを選ぶべきか
薬局やドラッグストアに並ぶ”市販品”の歯磨き粉、そして歯科医院でおすすめされる“専売品”の歯磨き粉。
「結局どっちがいいの?」「違いはあるの?」と疑問に思われたことはありませんか?
市販品と歯科専売品の違い、そしてどんな方にどちらがおすすめかを、以下にまとめます。
| ポイント | 市販の歯磨き粉 | 歯科医院専売の歯磨き粉 |
| 有効成分の濃度 | 比較的低めでマイルド | 濃度や配合バランスが専門的に設計されている |
| 成分の種類・配合 | 基本的な成分が中心 | 複数の抗炎症・殺菌成分を複合配合していることが多い |
| 効果の即効性・持続性 | 効果はゆるやか | 臨床データに基づいた効果的な処方 |
| 価格 | 安価で手軽 | やや高価だが効果重視の患者向け |
| 使い方の指導 | 自己判断が多い | 歯科医師や衛生士からの使用指導を受けられる |
〈どちらを選ぶべきか?〉
軽度の歯肉炎予防や日常ケアには、市販品でも十分な効果が期待できる場合がありますが、
既に歯周病の兆候がある方や予防効果を高めたい方は、歯科医院専売の高機能歯磨き粉をおすすめします。
特に、慢性的な歯ぐきの腫れや出血が気になる方は、専門成分配合の製品を使い、定期的に歯科検診を受けることが大切です。
歯ブラシと補助用具の正しい選び方・使い方

歯周病ケアに適した歯ブラシの特徴
- 毛の硬さ:柔らかめ(ソフトタイプ)がおすすめ
→ 硬い毛は歯ぐきを傷つけ、炎症を悪化させる可能性があります。
- ヘッドの大きさ:小さめでコンパクトなものが使いやすい
→ ヘッドが小さいと狭い口腔内や奥歯、歯間部にアクセスしやすいです。
- 毛先が細くて丸い加工のもの
→ 歯周ポケットや歯と歯ぐきの境目に優しく届きやすいです。
- 持ち手が握りやすく操作しやすい形状
→ 細かい動きがスムーズにできるものが望ましいです。
デンタルフロス・歯間ブラシの効果的な使用法
デンタルフロス
- 狭い歯間(歯が隣接している部分)に適している
- フロスを約40cm切り出し、指に巻き付けて使用
- 歯の側面に沿わせて「C字カーブ」を描きながら上下に動かし、プラークを除去
歯間ブラシ
- 歯と歯の間に隙間がある場合に有効
- 自分の歯間のサイズに合った太さを選ぶことが重要(歯科医師に相談推奨)
- ゆっくりと優しく差し込み、往復運動で汚れをかき出す
- 強く押し込みすぎると歯肉を傷つけるため注意
電動歯ブラシと口腔洗浄器の活用方法
電動歯ブラシ
- 振動や回転で効率的にプラーク除去が可能
- ブラシの当て方は基本の手磨きと同様、毛先を歯と歯ぐきの境目に当てることを意識
- 強く押し当てず、機械の動きを活かすことがポイント
歯周病のある方は、刺激が強すぎないモードやヘッドを選ぶと良いです。
口腔洗浄器(ウォーターフロス)
- 水流で歯周ポケットや歯間の汚れをやさしく洗い流す補助器具
- フロスや歯間ブラシが使いにくい方、インプラント・矯正装置装着中の方に特に効果的
ただし、単独では不十分なため、基本のブラッシングと併用することが大切です。
歯周病を予防する生活習慣とリスク管理
食事と栄養:歯周病予防に効果的な食べ物・避けるべき食品
歯周病といえば「歯磨きや定期健診が大切」と思われがちですが、実は日々の食生活も予防に大きく影響します。
歯ぐきを健康に保つために積極的に摂りたい栄養素と食品、そしてできれば控えたい食べ物について、歯科医の視点からご紹介します。
〈歯周病予防に良い食品〉
| 栄養素・食品例 | 期待できる効果 |
|---|---|
| ビタミンC (柑橘類、イチゴ、ピーマンなど) | 歯ぐきの健康維持、コラーゲン生成促進 |
| カルシウム (乳製品、小魚、緑黄色野菜など) | 骨の強化、歯の支持組織の維持 |
| ビタミンD (魚、きのこ、日光浴) | カルシウムの吸収促進、免疫機能のサポート |
| タンパク質 (肉、魚、大豆製品) | 組織修復と免疫力向上 |
| 食物繊維 (野菜、果物、穀物) | 口内の清掃効果、唾液分泌促進 |
〈避けるべき食品〉
- 糖質・精製炭水化物(甘いお菓子、清涼飲料水、白米・パンなど)
プラーク(歯垢)中の細菌の栄養源になり、歯周病リスクを高める
- 過度のアルコール摂取
口内環境を悪化させ、免疫力を低下させる
- 過度に硬い食品や極端に粘着性の高い食品
歯ぐきへの負担やプラーク残留の原因になる場合がある
禁煙・ストレス管理が歯周病に与える影響
禁煙が歯周病予防に与える影響
タバコは、歯周病の最大のリスク因子の一つです。
〈喫煙による影響〉
- 歯ぐきの血流が悪化→酸素や栄養が届きにくく、組織の回復が遅れる
- 免疫力の低下→歯周病菌に対する防御力が弱くなる
- 自覚症状が出にくい→出血や腫れが隠れて進行に気づきにくい
- 治療の効果が出にくい→歯石除去や歯周外科の効果が半減
喫煙者は非喫煙者に比べて2〜6倍も歯周病になりやすいという研究もあります。
また、インプラントや再生治療の成功率にも影響を与えるため、禁煙は歯科治療においても非常に重要なステップです。
ストレス管理と歯周病の関係
「心の状態」と「お口の健康」がつながっているのは、意外かもしれません。
ですが、実際にはストレスが歯周病の悪化に関わっていることが、近年の研究でも明らかになってきました。
〈ストレスによる影響〉
- 免疫力の低下→細菌に対する防御が弱まり、炎症が起きやすくなる
- 食生活の乱れ→栄養バランスの低下・甘いものの過食
- ブラッシングの質が下がる→疲れや気分の低下でケアが雑になる
- 歯ぎしり・食いしばりの増加→歯ぐきや歯周組織への負担が大きくなる
特に仕事や家庭で強いストレスを感じている方は、知らないうちに歯ぐきの状態が悪化していることもあります。
歯周病セルフケアでよくある質問

歯茎から血が出るけど磨き続けて大丈夫?
はい、正しい方法で磨き続けることが重要です。
歯ぐきからの出血は歯周病や歯肉炎のサインですが、磨くのをやめると状態が悪化します。
ただし、強くゴシゴシ磨くのは逆効果なので、やさしく毛先を歯ぐきの境目に当てて丁寧に磨きましょう。
気になる場合は歯科医院でチェックを受けてください。
市販の歯磨き粉で本当に効果はある?
一定の効果は期待できますが、成分や使い方がポイントです。
抗炎症成分や殺菌成分が含まれる歯磨き粉は、歯周病予防に役立ちます。
ただし、あくまで補助的な役割なので、正しいブラッシングと併用することが大切です。
症状がある場合は歯科医院専売の製品も検討しましょう。
セルフケアだけで歯周病は治る?
軽度の歯肉炎ならセルフケアで改善可能ですが、中等度以上は専門治療が必要です。
セルフケアは歯周病の進行予防と軽度症状の改善に有効です。
しかし、歯石除去や歯周ポケットの深い部分のケアは歯科医院での処置が必須です。
自己判断せず、定期的に専門医の診断を受けましょう。
電動歯ブラシと手磨き、どちらが効果的?
どちらも正しく使えば効果的ですが、電動歯ブラシはプラーク除去を効率化します。
電動歯ブラシは振動や回転で歯垢を落としやすく、特に磨き残しやすい奥歯や歯間のケアに有利です。
ただし、使い方が雑だと効果は薄れます。
手磨きも正しいテクニックを身につければ十分効果的です。
自分に合った方法で継続することが重要です。
まとめ
歯周病は、初期には自覚症状がほとんどなく、気づかないまま進行しやすい病気です。
歯ぐきの炎症から始まり、放置すると歯を支える骨が溶けて歯がぐらつき、最終的には歯を失うリスクもあります。
しかし、毎日の正しいセルフケアと生活習慣の改善、そして定期的な歯科医院での専門的な検診・クリーニングによって、十分に予防・進行抑制が可能です。
気になる症状があれば自己判断せず、速やかに歯科医師に相談しましょう。
健康な歯ぐきを守り、生涯自分の歯で食事を楽しめるよう、日々のケアを大切にしましょう。
